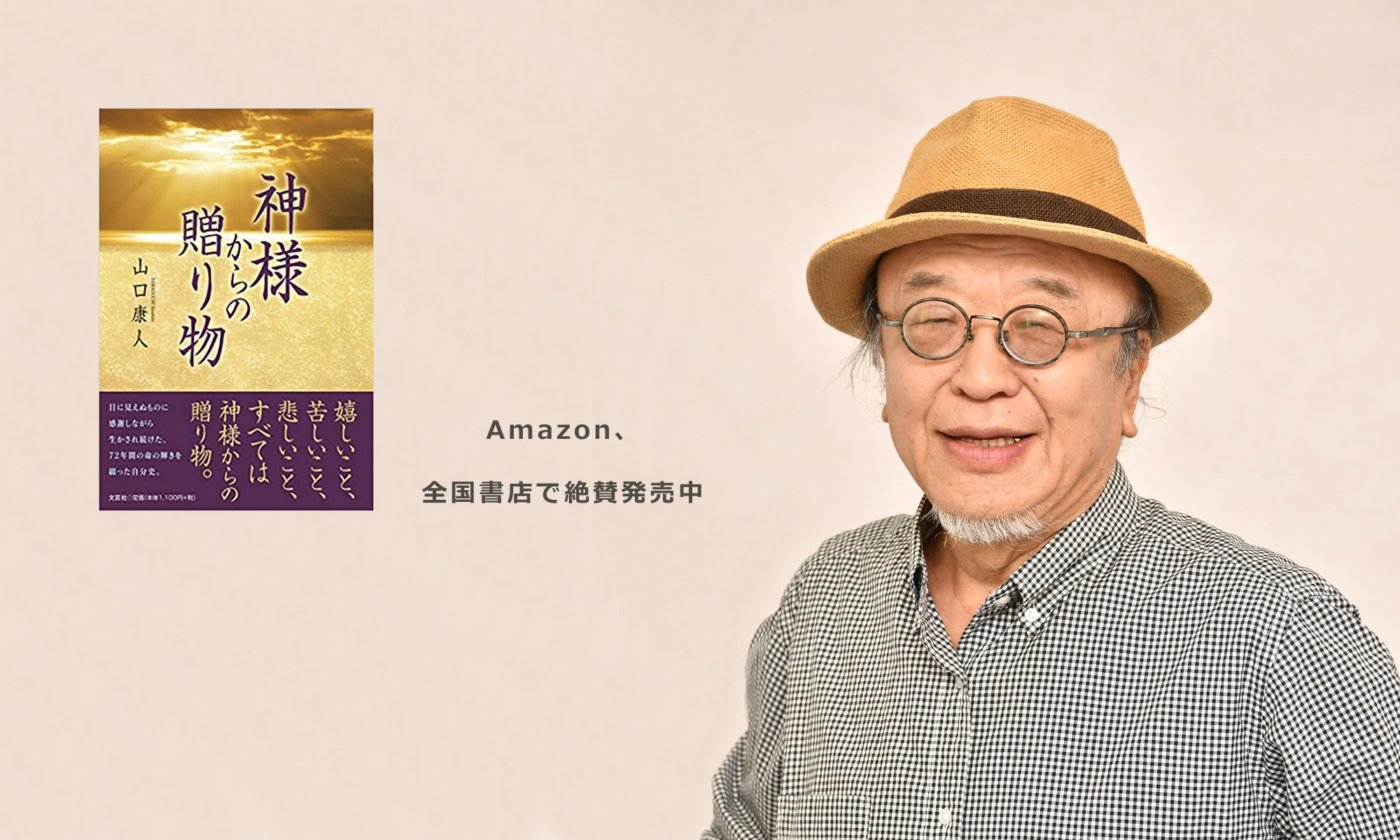いつも顔をだす、デパートの全国職人展示館にはお雛様が飾られてました。


そうですね、もうまもなく節句のひな祭り。

孫の明里が女の子ですから、お雛様を飾るでしょう。


そんなお雛様のかわいらしい人形を見てると節句の由来などを調べて見ました。
和暦(太陰太陽暦)の3月の節句(上巳)である3月3日(現在の4月頃)に行われていたが、明治6年(1873年)1月1日の改暦以後は一般的にグレゴリオ暦(新暦)の3月3日に行なう。しかし一部では引き続き旧暦3月3日に祝うか、新暦4月3日に祝う(東北・北陸など積雪・寒冷地に多い)。旧暦では桃の花が咲く季節になるため「桃の節句」となった。
形式 [編集]「男雛」と「女雛」を中心とする人形を飾り、桃の花を飾って、白酒や寿司などの飲食を楽しむ節句祭り。本来「内裏雛」とは雛人形の「男雛」と「女雛」の一対を指すが、男雛を「お内裏様」、女雛を「お雛様」と呼ぶ誤りは童謡「うれしいひなまつり」の歌詞から一般化してしまっている。関東雛と京雛では男雛と女雛の並ぶ位置は逆。三人官女以下のその他大勢の随臣、従者人形を「供揃い」という。
歴史 [編集]「雛祭り」はいつ頃から始まったのか歴史的には判然としないが、その起源説は複数存在している。平安時代の京都で既に平安貴族の子女の雅びな「遊びごと」として行われていた記録が現存している。その当時においても、やはり小さな御所風の御殿「屋形」をしつらえ飾ったものと考えられる。初めは「遊びごと」であり、儀式的なものではなく其処に雛あそびの名称の由来があった。しかし平安時代には川へ紙で作った人形を流す「流し雛」があり、「上巳の節句(穢れ払い)」として雛人形は「災厄よけ」の「守り雛」として祀られる様になった。
この日には、日本の宮廷において節会と呼ばれる宴会が開かれた。年間にわたり様々な節句が存在しており、そのうちの5つを江戸時代に幕府が公的な行事・祝日として定めた。新暦では3月3日・5月5日・7月7日は同じ曜日となる。
五節句 [編集]人日(じんじつ)
1月7日、七草
上巳(じょうし/じょうみ)
3月3日、桃の節句、雛祭り
端午(たんご)
5月5日、菖蒲の節句
七夕(しちせき/たなばた)
7月7日、たなばた、星祭り、竹・笹
重陽(ちょうよう)
9月9日、菊の節
日本5節句のひとつとしてのひな祭りですね。

もう少したら春が来ます。
この寒さももう少しの辛抱です。
早く来い、春 春、春
いや其の前にバレンタイー。
今年は1個かな、100個かな。
嬉しくもあり、またさびしくもありますね。